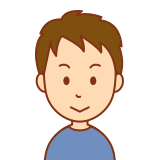
- 営業職を続けているが、HSP気質が影響して仕事が辛い
- すぐにでも転職したいが、また同じ失敗を繰り返さないか不安
- 営業職以外の経験がなく、異職種への転職に自信が持てない
そんな悩みを抱えるHSP営業マンに向けて、僕自身の経験をもとに解説していきます。
HSP営業が職場選びで最優先すべきは、何をしたいかではなく働く環境です。
- 誰と働くか(人間関係)
- どのように働くか(仕事の仕方)
- どんな規模の職場か(職場の大きさ)
私自身、6回の転職を繰り返す中で、この3つが転職先を選ぶうえでとても重要だと実感しました。
チャレンジ目的や会社都合による転職もありましたが、振り返ると長く働き続けられた職場、また働きたいと思えた職場には、「環境によるストレスの少なさ」が共通しています。
※関連記事:HSP気質の方が転職活動を進める際の全体像を把握したい方は、こちらのガイドも参考にしてください
※関連記事:HSP気質の方が転職活動を進める際の全体像を把握したい方は、こちらのガイドも参考にしてください
相手の立場に立った行動が取れる、穏やかな人が多い環境を選ぶ
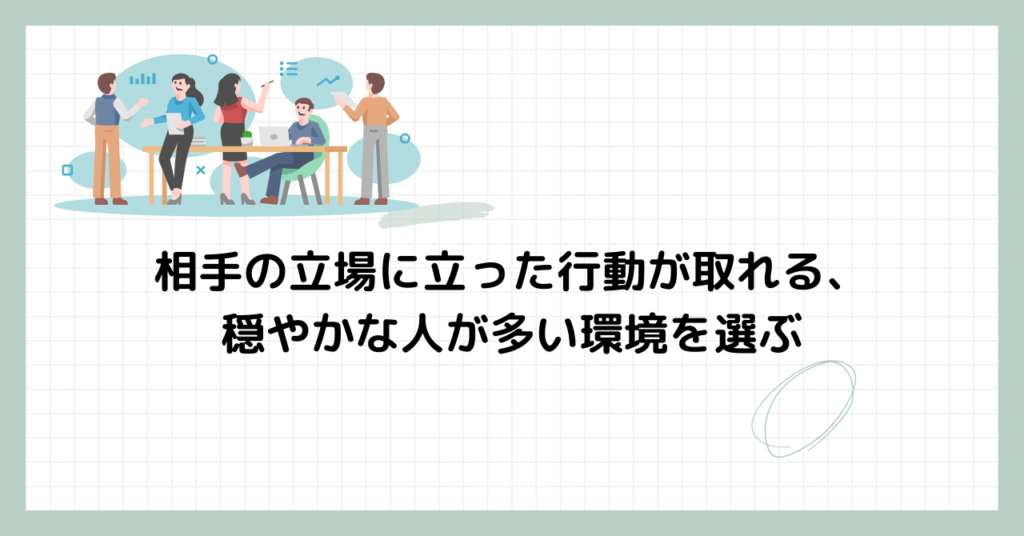
HSPの人は、他人の感情の変化に敏感であり、周囲の影響を受けやすい傾向があります。そのため、誰と一緒に働くかは、職場選びにおいて非常に重要なポイントです。
特に営業職では、貪欲でガツガツしたタイプの人が多く、他の職種以上に注意が必要になります。環境によっては、強い圧にさらされて心身が疲弊してしまうかもしれません。
HSPの人にとっては、相手の立場を考えながら感情をコントロールできる、落ち着いた人と一緒に仕事をする環境が、より安定して働き続けるために欠かせない要素となります。
会社自体が顧客本位で活動しているかを確認する
誰と仕事をするかを見極めるうえでも、会社全体が顧客に寄り添った活動を実践しているかを確認することが重要です。
営業職である以上、数字目標から完全に逃れることはできません。しかし、「売れればよい」という考え方が根付いている環境では、HSP気質の人が無理なく働くのは難しくなります。
私自身も、想いに共感して入社し、実際に働いてみてもギャップがなかった会社が2社ありました。
- 無理な金額の不動産を勧めない方針を徹底していた不動産会社(FP部門に在籍)
- 情報の提供価値を最重視し、ノルマが本当に存在しなかったポータルサイトメインの保険代理店
どちらの会社にも共通していたのは「正しい情報を真摯に顧客へ届ける」という姿勢が一貫していたことです。また、職場には落ち着いた雰囲気の人が多く、非常に働きやすさを感じました。
会社選びでは、以下の点に注意しましょう。
- 社長のコメントと、その考えに至った背景
- それによって生まれた企業の価値観や行動指針
エントリーや面談を進める前に、会社のスタンスや想いに共感できるかを、しっかり確認することが大切です。
喜怒哀楽が激しい、思考が読めないマイペースな人が身近にいないか
職場を選ぶうえで、喜怒哀楽が激しい人や思考が読めないマイペースな人が周囲にいるかどうかも重要なチェックポイントになります。
- 喜怒哀楽が激しい人
- 思考が見えないマイペースな人
一見、対極の性格に見えるかもしれません。しかし、どちらも「相手がどう考えるかを深く意識せずに行動する」という共通点を持っていると私は考えています。
もし、関わっている相手が怒っていたり、不機嫌だったりすると、HSPの人はつい考え込んでしまいやすい傾向があります。
私自身も、
- 自分の発言が相手にどう受け取られたのか
- 発言のニュアンスに問題があったのではないか
- 本当はこう伝えるべきだったのではないかと
考えがぐるぐると巡り、気づけば一人で頭がパンクしてしまうことが何度もありました。
その結果、目の前の業務に集中できなくなり、さらにストレスを感じてしまう悪循環に陥ることがありました。
僕がとても苦労したケースを2つ紹介します。
全てにお伺いが必要で感情が顔に出る女性社長
私が過去に在籍していたある会社では、何かを進める際、基本的に社長へ事前に話を通す必要があり、常時このような状態でした。
- 社長は感情がすぐ顔に出る方で
- 伝える内容がどう受け取られるか、常にヒヤヒヤしながら報告し
- 気持ちが落ち着くことがない
さらに社長は外出も多く、帰社したタイミングで適切な感情状態かどうかを見極めてから話しかける必要があり、伺いを立てるだけでも、次のような点を考える必要です。
- いつ社長が戻ってくるのか
- 今の社長の感情は適切か
- どのような表現で伝えるべきか
こうしたことを常に考え続けた結果、本来進めるべき業務に集中することが難しくなっていきました。
社内にはあっけらかんとした性格の人も多く、当時はなぜなのか不思議に思っていましたが、今振り返ると納得できます。
また、職場では人の文句も多く飛び交っていたため、「自分も陰で何か言われているのではないか」と気にすることが増え、HSP気質で周囲を気にしすぎる私にとっては、非常に辛い環境でした。
何を考えているかわからないマイペース社長
以前、人数規模が5名という小さな会社に在籍していたことがあり、ほぼ社長と私の2名で日々の業務を進めていました。そこでの苦労の話です。
- ほぼ社長と2名で活動
- マイペースすぎて相手の思考が読めず
- 常に一緒に行動するなかで、とても苦労
例えば、一緒に外出する際、私は時間にゆとりを持って行動したいタイプですが、
社長はギリギリまで動かないため、出発からストレスを感じる場面が多くありました。
中でも特に負担だったのは、前後の文脈もないまま唐突に質問や話題を投げかけられることです。たとえば、
「〇〇君ってこれについてどう思う?」
と突然聞かれるイメージです。
何が困るかというと、その質問に至る背景や意図がまったく説明されないことです。加えて、私が返した回答に対しても特にリアクションがなく、結果的に「自分はどう答えればよかったのか」がわからないまま思考が露頭に迷ってしまいました。
私としては、
「このやり方についてこう考えている。こうしたいと思っているが、〇〇君はどう思う?」
のように、前後の流れを踏まえて質問してもらえると考えやすいと感じていました。
- 質問の意図や、話の前提が何なのか
- そもそも相手がどう考えているのか
- 単純に質問しているだけなのか
- 同調を求めているのか
- 自分の意見を引き出したいのか
- それとも説教をしたいのか
こうした点が、まったく読み取れませんでした。
自分の意見を伝えるよりも、相手の感情を尊重しようとするHSP気質の私にとって、
相手が何を考えているのかわからない状況は、非常に大きなストレスとなりました。
面談時に人との相性の違和感がないかを確認する
今紹介した2社については、面談で社長と直接話した際に相性に対する違和感を覚えていました。具体的には、次のような感覚です。
- 話しているときに感じる相手からの圧力
- 会話の居心地の悪さ
しかし、その違和感には目を瞑り、やりたい仕事を優先して入社を決めた結果、結局はその違和感が一番のストレスとなり、退職に至りました。
- 一緒に働く人とは、できる限り事前に会話をしてみること
- 会話の居心地が良い環境を優先して選ぶこと
この2点は、HSP気質の人にとって、職場選びで特に重要なポイントです。
顧客の相談相手になれる営業方法の会社を選ぶ
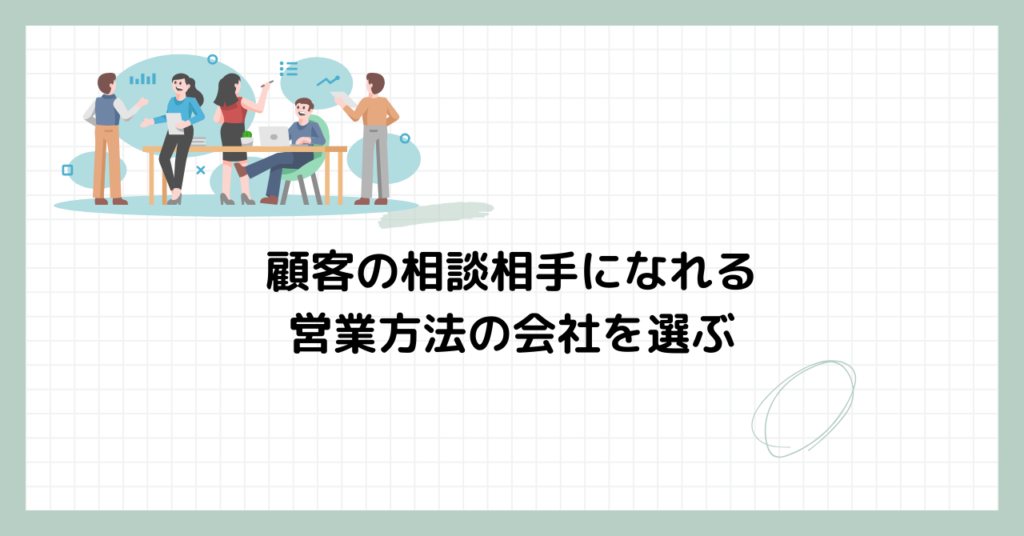
相手の気持ちを繊細に汲み取り、配慮できるHSPの人にとって、「顧客にとっての相談者」という立ち位置は、持ち前の能力を最も発揮できる環境になります。
一方で、テレアポや飛び込み営業など、興味を持たれていない顧客に対するアプローチは、
断られることが前提となるため、大きなストレスを感じやすくなります。
どの状態の顧客と接点を持つかは、HSPが力を発揮できるかどうかに直結するため、
職場選びにおいて非常に重要なポイントです。
顧客が話を聞きたいという関係性をどの程度持てるか
HSPの人が比較的活動しやすい営業スタイルには、次のような形式があります。
(新規)
- 来店型で、お客様から来訪される店頭営業
- 顧客から問い合わせが入った後の営業
- 別部隊がアポイントを設定したうえでの営業
(既存)
- 取引のある顧客のルート営業
- 既存顧客へのカスタマーサクセス業務
状況や組織体制によっては、新規と既存の両方を担当する場合もあります。
しかし、重要なのは顧客側に「話を聞いてもらえる姿勢」があり、一定の受け入れ態勢が整っているかどうかです。
仮に新規開拓を担当する場合であっても、以下の点を事前に確認しておくことが大切となります。
- テレアポなどを通じて、自ら商談先を開拓する必要があるのか
- 何らかの形でアポイントが設定された状態からスタートできるのか
- 商談が設定されていない場合でも、問い合わせが入った顧客にアプローチできるのか
私が過去に成果を上げた事例についても、これらの条件を満たしている環境でした。
不動産営業が設定してくれるFP相談
以前、私は某不動産会社のFP業務部門に所属していたことがあります。
不動産を購入したいという顧客に対し、ファイナンシャルプランナー(FP)としてサポートに入りました。
業務内容は、次のようなシミュレーションを行い、営業部門にフィードバックすることです。
- 適切な価格の不動産かどうか
- ローン破綻しないか
- 家計バランスは問題ないか
営業的な側面では、保険の見直し提案も行い、保険の売上にもつなげていく役割を担っていました。この環境で特に良かった点は、完全に「先生的な立ち位置」で顧客対応ができたことです。
- 顧客の悩みを丁寧に汲み取りながら進めることができた
- HSPの特性である相手を察する力を大いに発揮できた
- 結果として、顧客から高い信用を得られた
この業務では、会社や保険会社から表彰されるなど、自分の中でも大きな成果を残すことができました。
さらに社長からも「無理な金額を勧めるとお客様が不幸になる。絶対にやめろ」と強く言われており、不動産を無理に勧めるような営業活動は、むしろ叱責される環境です。
そのため、本当に顧客本位で業務を進められた点も、私にとって非常に大きな安心材料となりました。
顧客から問い合わせが入った上での新規営業
現在も似たような形で、私は営業活動を行っています。
基本的に、顧客が話を聞きたいと自ら問い合わせをしてきた上で、商談に入るスタイルです。
当然ながら、最初から顧客側に興味関心があるため、商談中もきちんと話を聞いてもらいやすい環境になっています。
ただし、組織である以上、将来的な体制変更により、テレアポが必要になる可能性もゼロではありません。そのため、事前に組織編成や今後の営業方針についても確認しておくことが重要です。
影響範囲の少ない、規模の小さい環境を選ぶ
HSPの特徴として、人に見られている状況では、周囲の視線を強く意識してしまい、結果的に本来の力を発揮できなくなる場面が多くあります。
さらに、繊細な気質ゆえに、誰かから何かを指摘された際には、自分自身を否定されたように感じ、大きなダメージを受けることも少なくありません。
- 人が多いオフィスでは電話に出るのが億劫になり、周囲に聞こえないよう声が小さくなる
- 上司に営業同行されると、自分の対応が正しいか不安になり、耐えられなくなる
- メールのCC欄に多くの人が入ると、怖くて送信しづらくなる
このように、周囲の視線が気になりやすい場合は、次のような環境を選ぶことも重要です。
- 人に見られていても、自分の対応に自信が持てる環境
- まだ自信がなくても、人に見られにくい環境
自分の経験に自信を持てる規模の小さい立ち上がったばかりの環境
ある程度出来上がった場所ではなく、これから一緒に作り上げていく環境を選ぶことが大切です。比較的人数も少人数となるため、働きやすさの面でも一石二鳥と言えます。
具体的には、次のような環境が該当します。
- 新しい事業の立ち上げ部門
- 起業して間もないスタートアップ企業
- 新しい店舗の立ち上げメンバー
このような状況に身を置くことで、自分自身が経験値として最も高い位置に立てるため、日々の行動にも自然と自信が持てるようになり、周囲の目も気になりにくくなります。
僕の思い当たる立ち上げに携わった業務歴
私自身、過去を振り返ると次のような立ち上げに関わってきました。
- 居酒屋のオープニングスタッフ(学生時代のアルバイト)
- 数百名規模の会社で、数名での新規事業立ち上げに参加
- 設立間もないスタートアップ企業(当然小人数)
最初から携わることで、スタートラインは皆同じになります。その中で知識や経験を積み重ねていくため、日々の行動にも自信が持てるようになりました。
冒頭でも触れたように、「何をしたいか」ではなく、「どの環境が自分にとって働きやすいか」
という視点を持つことが、HSPの人にとって非常に重要です。
立ち上げに携わることのメリットとストレス
組織がまだ固まっていない立ち上げ期は、業務の自由度が高く、自分の意見やアイディアを反映しやすい環境になります。
しかし、最も大きなストレス要因は「数字」に関するプレッシャーです。
常に新しいことに取り組みながら、PDCAサイクルを回し続ける必要があり、HSPの人にとっては精神的な負担が非常に大きくなりがちです。
さらに、HSPの特性として、将来の見えないことに対して仮説を立てて進めることが苦手です。
計画を立てる段階で、細かな違和感を覚えてしまうと、思うように前に進めなくなるケースも多くありました。
こうした不安を感じる場合は、規模は小さくても業務が安定している企業に携わる選択を取るのも有効です。
組織化した環境に身を置くストレス
一方で、組織化が進んだ環境には、特有のストレスも存在します。
周囲から見られること、指摘を受けること、常に何かを発信するなどはHSPにとって大の苦手です。
たとえば次のようなことが挙げられます。
- 電話対応や商談の様子を録音・録画して、みんなで振り返りを行う
- 日々の行動が数値管理され、常にチェックされる
これらは営業組織としてはごく一般的な取り組みであり、組織運営の観点からは正しい施策です。しかし、好き嫌いという観点では別問題です。
HSP気質を持つ人は周囲から干渉を受けにくい、属人的な業務スタイルの方が圧倒的に働きやすく感じます。そのため、職場を選ぶ際には、日々の活動がどれくらいの自由度を持って行えるかを事前に確認しておくことが重要です。
周りに人が少ない、またリモート業務の環境
理想を言えば、リモートで一人で作業できる環境が最も働きやすいと感じます。

私の場合、極端な話、テレアポ業務であっても、一人で黙々と取り組むスタイルであれば、十分に頑張ることができます。
過去を振り返ると、リモート勤務以外でも、次のような環境でストレスを抑えて働けていました。
- 新規事業の立ち上げ時、オフィスの中2階にある空きスペースを事務所にして少人数で業務
- 本社事務所とは別に設けた分室で、限られた人数だけで業務
- フリースペースや個室ブースを活用し、人目につかない場所で作業や電話対応
このような環境は積極的に選べるとは限りませんが、ワンフロアに多数の人が在籍している職場と比較すると、ストレスの軽減効果は非常に大きいです。
側から見ると多少見窄らしい環境であったとしても、HSPの私にとっては、落ち着いて働ける大切な要素となっていました。
働く場所を選ぶ際には、人目につきにくい環境かどうかも、ぜひ一つの判断基準にしてみてください。
HSPとして営業職を続けていく上で、職場選びは非常に重要なテーマになります。
自分に合った環境を見つけることで、ストレスを大きく軽減でき、持ち前の繊細さや共感力を最大限に活かしながら、仕事に取り組むことができます。
これまで紹介してきた3つのポイントを参考に、皆さん自身にとって最適な職場を見つけ、充実した営業活動にチャレンジしてみてください。
職場環境をしっかり見極め、自分のペースで成長していければ、HSPであることを強みに変えられるフィールドをきっと見つけることができます。
🔍 より自分に合った職場を探したい方へ
HSPに理解のある転職エージェントを活用すると、環境選びもグッとラクになります。
➡️ HSPにおすすめの転職エージェント5選|タイプ別比較はこちら
※関連記事:HSP気質の方が転職活動を進める際の全体像を把握したい方は、こちらのガイドも参考にしてください
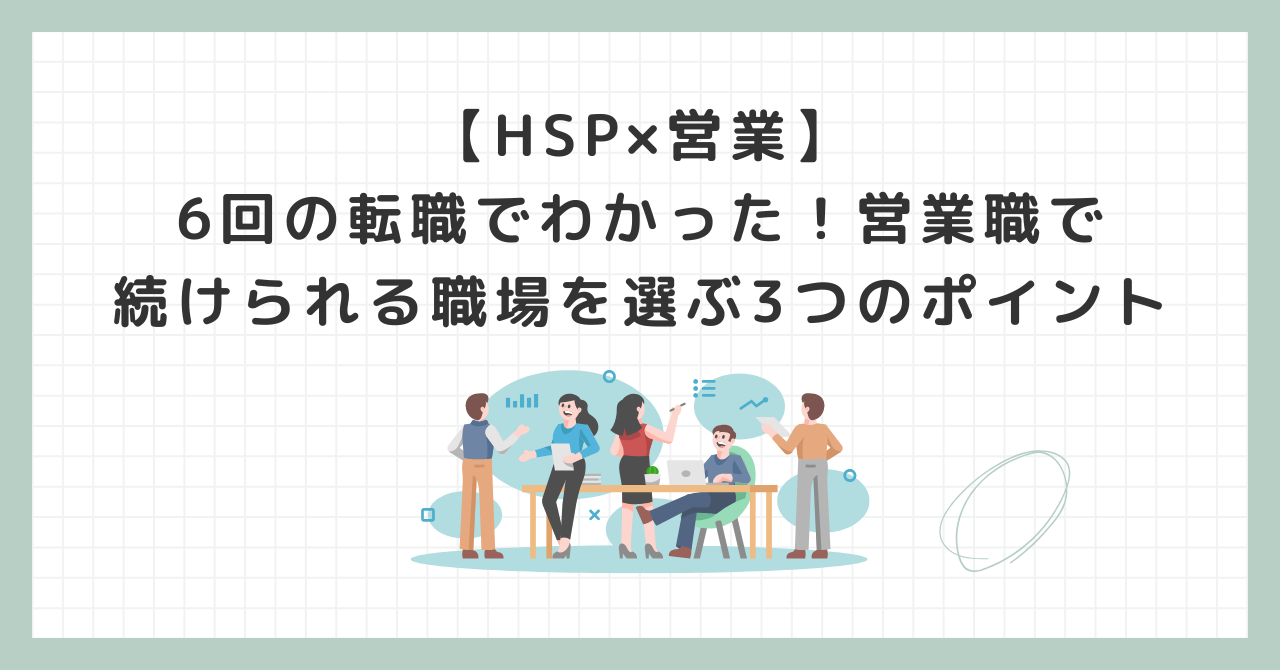


コメント